2015年09月18日
長良の足についてこれる?-牛深第十景その二
こんにちは!
はじめましての人ははじめまして!
続きものです。その一→こちら
牛深の事で軍艦長良を学ぶにはこの本を読まないわけにはいかないということで読ませていただきました。

島一春著「天草灘にひびけ鎮魂の譜」1995年。
戦後50年のときということで今から20年前。最近古文書とか読んでたから20年前でも最近に思う、笑。
天草出身の作家島一春氏がラジオ番組の取材で牛深へ何度も訪れ一人のおばあちゃんにインタビューする事がきっかけでこの本がうまれました。
冒頭。『天草を描くには天草の海をしらなければならない。天草の海を知るには、肥後随一の漁業の町である牛深の歴史や、そこに生きた人びとの哀歓にふれ、海のうねり、磯の香や風のささやきにふれなくてはならない、とわたしは思った。』と書いてありました。
天草を知るには牛深を知らないといけないと見識のある方が文字に残してくださっている。嬉しいことですね。
その牛深で長年私財を投じて軍艦長良戦没者の供養をひそやかに続けていた人がいました。
名を「佐々木つる」さん。このブログでは私の母がお世話になっていたこともあり、母が呼んでいる「おつるおばさん」と親しみを込めてこれから表記致します。
この本はおつるおばさんの一生を振り返り、なぜ自分の身内が亡くなったわけではないのに一人の女性が長年毎日毎日長良の供養を行ってきたのかを探るノンフィクションです。この中に牛深の紹介で遠見番所の事も書かれていましたし、牛深にまつわる明治維新の頃の事も書かれていました。その辺りは御番所ブログで後日纏めます。
おつるおばさんは尋常小学校卒業後鹿児島東郷へ父とともに渡る。
東郷の地では日清、日露戦争に従軍した元軍人が何人もいておつるおばさんはその方達より戦争体験をよく聞いていた。
そして父から話を聞いていた太平記の楠木正成とその子正行の戦物語に感動を覚えた。この二つの話の共通点である死を顧みずに国のために戦うこと。その純烈さにおつるおばさんは人間の生命の炎のような燃焼を感じとったそうだ。
明治45年、母が病になった知らせを聞いたおつるおばさんは牛深へ戻ってくる。
母の代わりに弟たちを育てるため母の青果の仕事を受け継ぐ。14歳だった。
大正12年染屋(牛深では旗屋、主に祝旗や大漁旗を染めるため)に嫁ぐ。
染屋は何度も水洗いをするため大量に水を使う。水資源が乏しかった牛深ではその水汲みが大変な重労働だった。その仕事は身重のおつるおばさんの仕事だった。
娘さんが産まれ素直にすくすく育った。
娘さんが小学3年生になった頃、牛深には軽巡夕張、軽巡長良、その他駆逐艦が湾内に碇泊することがあった。
牛深の人たちは海岸に集まり万歳を叫び、艦上では水兵さんが手を振り返した。
娘さんが軍艦に乗ってみたいと言う。だがこの希望をおつるおばさんの力では叶えてあげることができないのは当たり前のことだった。
しかし娘さんは軍艦に乗ってみたいと事あるごとに言っていたのでしょう。その話が軍人さんの元へ届き、長良の水兵さんが娘さんに艦内を見せてくれたのだそうだ。帰りにキャラメルなどのお菓子もおみやげに持たせてくれたそうだ。
これがおつるおばさんと長良の出会いである。
それから2.3年の時間が経った。その後長良は牛深へ来てなかったようだった。
娘さんが七夕の短冊に書いた願いの一つに、「長良よ永遠に」と書いているのを見てまだ覚えているんだとおつるおばさんは思って心に残った。
牛深は平和であったが、海を隔てた場所では満州事変から盧溝橋事件へ全面戦争が始まろうとしていた。
次第に牛深でも若者が出征していき宮崎八幡宮での兵隊見送りが町を上げての盛大な行事になった。
夫は体を悪くしたためおつるおばさんは休まず働いた。熊本へ仕事で出た時は海軍へ献金も行っていた。海軍へ献金したのは長良への感謝の気持ちと娘さんが海軍好きだったからだった。
昭和18年5月21日
山本五十六連合艦隊総司令官の戦死が一般に発表された。
昭和天皇が終日ご文庫にて籠もられお慎みなられたあのときのことだ。関連→昭和天皇に日本の心を見た-その1
記録のためにもう少し詳しく。
4月18日、最前線で戦う兵士を鼓舞するため山本長官と参謀長が2機の攻撃機に分乗しバラレ島に向かった。
しかし米軍は日本の行動電報を解読し2機を奇襲。1機は海中、1機はジャングルへ墜落した。
ジャングルへ墜落した方には山本長官が乗っていて、機銃弾を頭と胸に受け日本刀を両膝の間に挟んで端然と座席に座ったまま絶命していたと言われている。
日本は山本長官を失ったことで国民の心に大きな風穴を開けた。
長官の国葬6月5日、牛深では町にサイレンが鳴り響き海辺でも家庭でも、海上でも全員が黙祷を捧げ冥福を祈った。
おつるおばさんはこのとき東に向かって深々と頭を下げ、止めどない涙を流したそうだ。
*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪
そして運命の昭和19年8月7日が訪れる。
その日おつるおばさんは須口へでかけ家路についていた。一瞬大気が震えた。
何が起こったかわからず海を見ると沖合に煙が立ち上っていた。
一方、天草灘を見張る軍の監視所では一隻の巡洋艦が通っているのを確認していた。
本渡の司令部へ電話連絡しようとした矢先、閃光が走り水柱が立ち昇るのが見えた。2発目の攻撃を受けた。
もう一度望遠鏡で沖合を見た。凪いだ真昼の海のかなたに、艦首を天にむけて沈没していく黒い艦影をはっきり確認して司令部へ連絡した。
大島沖合では牛深の漁師がマンビキ(シイラ)漁を行っていた。その漁師さんたちは度々牛深へ来る長良を見ていてそのとき通っていた軍艦が長良だとわかった。
漁を続けようとした所、閃光が走り水柱が起こった。長良の速度がみるみるうちに落ちていく。近くに居た牛深の漁師達は巻き込まれるのを恐れず全速力で助けに駆けつけたのだった。
漁船の救助により乗組員のうち235人は牛深の港へ上陸することが出来た。誇れる牛深先人たち。本当に素晴らしい勇敢な行動ですね。
ここの長良のことも、もう少し詳しく書いておきます。
長良は敵潜水艦に気がついていた。このとき潜水艦雷撃を避けるため有効な回避方法であるジグザク走行を行っていた。戦艦にはできない巡洋艦ならではの回避行動である。
米潜水艦クローカーの後部発射管から4本の魚雷が射出され、うち1本が長良の右舷後部に命中、艦首は天草の陸地を向いた。艦は傾きはじめ続く2発めの被弾で大きく振動し艦首を天へ向けた。
この直前中原義一郎艦長は落ち着き払った声で(このとき自身は死の覚悟を決めていたのだろう)「総員退去」の命令を発した。
長良には乗組員583人いたが生存者は上記した235人。中原艦長ほか347人の軍人は長良とともに天草の海底へ沈んだのである。
ただこのことは戦時中であったため、長良が沈んだことは日本国民にも知られてはならず、すぐさま軍の厳しい箝口令がしかれた。牛深の人同士でも話すことができなかった。
二十歳になっていた娘さんとおつるおばさんは二人で涙を流し長良艦の方達の冥福を心から祈ったという。
ここまでが本の前半です。ここから後半はおつるおばさんの慰霊の積み重ねが書かれています。お読みでない方々に読んでいただきたいので詳しくは纏めません。絶版になっているのかこの本の価格は値下がりしてなくむしろプレミアがついて高くなっているところもあるので新しく手に入れるのは少しむずかしいかもしれませんが牛深の方々は結構持ってらっしゃる?!かもしれないので持ってる方からお借りしてでも私と同年代または下の方々にぜひ読んでいただきたいです。
ボラ山の石塔が建てられる経緯や、そこに携わる牛深の方々の気持ち、海上慰霊の事。この牛深の先人の積み重ねをしっかり受け継いで行かないといけないと私も思っています。
終盤、長良の慰霊を続けてくれていた事を知った長良艦長婦人が後に牛深へ訪れるのですが、その前に取り急ぎおつるおばさんへ宛てた手紙も公開してありました。ここハンカチ何枚も用意したほうがいいですね。最初読んだときは新幹線の移動中だったため人前なのに涙がでるもんだからそれ以上読めなくて困りました、はは。
おつるおばさんが残してくれた慰霊のこころは今でも牛深の方達に残っている。
近年、戦艦武蔵(大和と同型)の沈んだ場所を米資産家が発見し引揚を検討というニュースを見た。
天草-長崎間には同じように沈んだ艦が潜水艦をはじめ複数あるそうだ。数ヶ月前だったと思いますが西日本新聞でそういう記事を読んだ。
ここで日本における沈んだ軍艦の考え方を補足して終わりにします。
日本では沈んだ軍艦は、乗組員方々の慰霊の為、またはその場所がお亡くなりになられた場所ということで場所の特定は行っても、引き上げる事は絶対行いません。艦そのものがその方々の墓標となるからです。この日本の考え方を一部を除くアジア諸国は理解尊重し引き上げることは考えなかった。
もちろん遺族も海底の映像は見たいと思われるでしょうが、引揚は希望しておられません。
この考え方を大事にしたいと私も思います。
軽巡長良が沈んだ場所は海底が砂だったため、沈んだそのままの姿で現在も艦首を天に向け安らかに眠っている。
それはまさしく長良が墓標そのもののようであるとの事。
現在の安保関連法案も同じ。おつるおばさんが残してくれた想いから平和を重んじ、戦争をしないために必要な事を考えないといけません。
米の戦争に日本が巻き込まれるとよく反対派が言っていますが、現実日本の問題に巻き込まれているのは米の方だということを理解しないといけません。
最新ネット世論調査の結果。

ネットは少し右寄りになるというか、興味持って調べたりする人たちが多いのでこういう結果になる。本来ならば一般がこういう結果にならないといけないと思う。それでも憲法改正だったとしたら過半数にはぎりぎり足りませんね。明らかに女性や若い世代はまだまだ勉強不足ですね。
全2回の予定でございましたが、長くなりすぎましたので予告しておりました艦これにつきましては次回雰囲気を変えて公開致します。
私もこの本にもっと早く出会うべきでした。艦これファンも読んでみて!絶対牛深へ訪れたくなるから!
その三→こちら
はじめましての人ははじめまして!
続きものです。その一→こちら
牛深の事で軍艦長良を学ぶにはこの本を読まないわけにはいかないということで読ませていただきました。

島一春著「天草灘にひびけ鎮魂の譜」1995年。
戦後50年のときということで今から20年前。最近古文書とか読んでたから20年前でも最近に思う、笑。
天草出身の作家島一春氏がラジオ番組の取材で牛深へ何度も訪れ一人のおばあちゃんにインタビューする事がきっかけでこの本がうまれました。
冒頭。『天草を描くには天草の海をしらなければならない。天草の海を知るには、肥後随一の漁業の町である牛深の歴史や、そこに生きた人びとの哀歓にふれ、海のうねり、磯の香や風のささやきにふれなくてはならない、とわたしは思った。』と書いてありました。
天草を知るには牛深を知らないといけないと見識のある方が文字に残してくださっている。嬉しいことですね。
その牛深で長年私財を投じて軍艦長良戦没者の供養をひそやかに続けていた人がいました。
名を「佐々木つる」さん。このブログでは私の母がお世話になっていたこともあり、母が呼んでいる「おつるおばさん」と親しみを込めてこれから表記致します。
この本はおつるおばさんの一生を振り返り、なぜ自分の身内が亡くなったわけではないのに一人の女性が長年毎日毎日長良の供養を行ってきたのかを探るノンフィクションです。この中に牛深の紹介で遠見番所の事も書かれていましたし、牛深にまつわる明治維新の頃の事も書かれていました。その辺りは御番所ブログで後日纏めます。
おつるおばさんは尋常小学校卒業後鹿児島東郷へ父とともに渡る。
東郷の地では日清、日露戦争に従軍した元軍人が何人もいておつるおばさんはその方達より戦争体験をよく聞いていた。
そして父から話を聞いていた太平記の楠木正成とその子正行の戦物語に感動を覚えた。この二つの話の共通点である死を顧みずに国のために戦うこと。その純烈さにおつるおばさんは人間の生命の炎のような燃焼を感じとったそうだ。
明治45年、母が病になった知らせを聞いたおつるおばさんは牛深へ戻ってくる。
母の代わりに弟たちを育てるため母の青果の仕事を受け継ぐ。14歳だった。
大正12年染屋(牛深では旗屋、主に祝旗や大漁旗を染めるため)に嫁ぐ。
染屋は何度も水洗いをするため大量に水を使う。水資源が乏しかった牛深ではその水汲みが大変な重労働だった。その仕事は身重のおつるおばさんの仕事だった。
娘さんが産まれ素直にすくすく育った。
娘さんが小学3年生になった頃、牛深には軽巡夕張、軽巡長良、その他駆逐艦が湾内に碇泊することがあった。
牛深の人たちは海岸に集まり万歳を叫び、艦上では水兵さんが手を振り返した。
娘さんが軍艦に乗ってみたいと言う。だがこの希望をおつるおばさんの力では叶えてあげることができないのは当たり前のことだった。
しかし娘さんは軍艦に乗ってみたいと事あるごとに言っていたのでしょう。その話が軍人さんの元へ届き、長良の水兵さんが娘さんに艦内を見せてくれたのだそうだ。帰りにキャラメルなどのお菓子もおみやげに持たせてくれたそうだ。
これがおつるおばさんと長良の出会いである。
それから2.3年の時間が経った。その後長良は牛深へ来てなかったようだった。
娘さんが七夕の短冊に書いた願いの一つに、「長良よ永遠に」と書いているのを見てまだ覚えているんだとおつるおばさんは思って心に残った。
牛深は平和であったが、海を隔てた場所では満州事変から盧溝橋事件へ全面戦争が始まろうとしていた。
次第に牛深でも若者が出征していき宮崎八幡宮での兵隊見送りが町を上げての盛大な行事になった。
夫は体を悪くしたためおつるおばさんは休まず働いた。熊本へ仕事で出た時は海軍へ献金も行っていた。海軍へ献金したのは長良への感謝の気持ちと娘さんが海軍好きだったからだった。
昭和18年5月21日
山本五十六連合艦隊総司令官の戦死が一般に発表された。
昭和天皇が終日ご文庫にて籠もられお慎みなられたあのときのことだ。関連→昭和天皇に日本の心を見た-その1
記録のためにもう少し詳しく。
4月18日、最前線で戦う兵士を鼓舞するため山本長官と参謀長が2機の攻撃機に分乗しバラレ島に向かった。
しかし米軍は日本の行動電報を解読し2機を奇襲。1機は海中、1機はジャングルへ墜落した。
ジャングルへ墜落した方には山本長官が乗っていて、機銃弾を頭と胸に受け日本刀を両膝の間に挟んで端然と座席に座ったまま絶命していたと言われている。
日本は山本長官を失ったことで国民の心に大きな風穴を開けた。
長官の国葬6月5日、牛深では町にサイレンが鳴り響き海辺でも家庭でも、海上でも全員が黙祷を捧げ冥福を祈った。
おつるおばさんはこのとき東に向かって深々と頭を下げ、止めどない涙を流したそうだ。
*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪
そして運命の昭和19年8月7日が訪れる。
その日おつるおばさんは須口へでかけ家路についていた。一瞬大気が震えた。
何が起こったかわからず海を見ると沖合に煙が立ち上っていた。
一方、天草灘を見張る軍の監視所では一隻の巡洋艦が通っているのを確認していた。
本渡の司令部へ電話連絡しようとした矢先、閃光が走り水柱が立ち昇るのが見えた。2発目の攻撃を受けた。
もう一度望遠鏡で沖合を見た。凪いだ真昼の海のかなたに、艦首を天にむけて沈没していく黒い艦影をはっきり確認して司令部へ連絡した。
大島沖合では牛深の漁師がマンビキ(シイラ)漁を行っていた。その漁師さんたちは度々牛深へ来る長良を見ていてそのとき通っていた軍艦が長良だとわかった。
漁を続けようとした所、閃光が走り水柱が起こった。長良の速度がみるみるうちに落ちていく。近くに居た牛深の漁師達は巻き込まれるのを恐れず全速力で助けに駆けつけたのだった。
漁船の救助により乗組員のうち235人は牛深の港へ上陸することが出来た。誇れる牛深先人たち。本当に素晴らしい勇敢な行動ですね。
ここの長良のことも、もう少し詳しく書いておきます。
長良は敵潜水艦に気がついていた。このとき潜水艦雷撃を避けるため有効な回避方法であるジグザク走行を行っていた。戦艦にはできない巡洋艦ならではの回避行動である。
米潜水艦クローカーの後部発射管から4本の魚雷が射出され、うち1本が長良の右舷後部に命中、艦首は天草の陸地を向いた。艦は傾きはじめ続く2発めの被弾で大きく振動し艦首を天へ向けた。
この直前中原義一郎艦長は落ち着き払った声で(このとき自身は死の覚悟を決めていたのだろう)「総員退去」の命令を発した。
長良には乗組員583人いたが生存者は上記した235人。中原艦長ほか347人の軍人は長良とともに天草の海底へ沈んだのである。
ただこのことは戦時中であったため、長良が沈んだことは日本国民にも知られてはならず、すぐさま軍の厳しい箝口令がしかれた。牛深の人同士でも話すことができなかった。
二十歳になっていた娘さんとおつるおばさんは二人で涙を流し長良艦の方達の冥福を心から祈ったという。
ここまでが本の前半です。ここから後半はおつるおばさんの慰霊の積み重ねが書かれています。お読みでない方々に読んでいただきたいので詳しくは纏めません。絶版になっているのかこの本の価格は値下がりしてなくむしろプレミアがついて高くなっているところもあるので新しく手に入れるのは少しむずかしいかもしれませんが牛深の方々は結構持ってらっしゃる?!かもしれないので持ってる方からお借りしてでも私と同年代または下の方々にぜひ読んでいただきたいです。
ボラ山の石塔が建てられる経緯や、そこに携わる牛深の方々の気持ち、海上慰霊の事。この牛深の先人の積み重ねをしっかり受け継いで行かないといけないと私も思っています。
終盤、長良の慰霊を続けてくれていた事を知った長良艦長婦人が後に牛深へ訪れるのですが、その前に取り急ぎおつるおばさんへ宛てた手紙も公開してありました。ここハンカチ何枚も用意したほうがいいですね。最初読んだときは新幹線の移動中だったため人前なのに涙がでるもんだからそれ以上読めなくて困りました、はは。
おつるおばさんが残してくれた慰霊のこころは今でも牛深の方達に残っている。
近年、戦艦武蔵(大和と同型)の沈んだ場所を米資産家が発見し引揚を検討というニュースを見た。
天草-長崎間には同じように沈んだ艦が潜水艦をはじめ複数あるそうだ。数ヶ月前だったと思いますが西日本新聞でそういう記事を読んだ。
ここで日本における沈んだ軍艦の考え方を補足して終わりにします。
日本では沈んだ軍艦は、乗組員方々の慰霊の為、またはその場所がお亡くなりになられた場所ということで場所の特定は行っても、引き上げる事は絶対行いません。艦そのものがその方々の墓標となるからです。この日本の考え方を一部を除くアジア諸国は理解尊重し引き上げることは考えなかった。
もちろん遺族も海底の映像は見たいと思われるでしょうが、引揚は希望しておられません。
この考え方を大事にしたいと私も思います。
軽巡長良が沈んだ場所は海底が砂だったため、沈んだそのままの姿で現在も艦首を天に向け安らかに眠っている。
それはまさしく長良が墓標そのもののようであるとの事。
現在の安保関連法案も同じ。おつるおばさんが残してくれた想いから平和を重んじ、戦争をしないために必要な事を考えないといけません。
米の戦争に日本が巻き込まれるとよく反対派が言っていますが、現実日本の問題に巻き込まれているのは米の方だということを理解しないといけません。
最新ネット世論調査の結果。

ネットは少し右寄りになるというか、興味持って調べたりする人たちが多いのでこういう結果になる。本来ならば一般がこういう結果にならないといけないと思う。それでも憲法改正だったとしたら過半数にはぎりぎり足りませんね。明らかに女性や若い世代はまだまだ勉強不足ですね。
全2回の予定でございましたが、長くなりすぎましたので予告しておりました艦これにつきましては次回雰囲気を変えて公開致します。
私もこの本にもっと早く出会うべきでした。艦これファンも読んでみて!絶対牛深へ訪れたくなるから!
その三→こちら
2015年09月12日
長良の足についてこれる?-牛深第十景その一
こんにちは!
はじめましての人ははじめまして!
「絵で見る~」の本についてはみなさんご注文いただき誠にありがとうございます。初版残り10冊ですお早めに!牛深の方は母へ言っていただけるとすぐお届けさせてもらいますm(__)m
今回は人気企画牛深八景の十作目。第十景でございます。題材は題名でお分かりの通り軍艦長良です。牛深に深く関係していて、まとめたいことが多くあるので2回に分けます。
昨日から鬼怒川の決壊でニュースは埋め尽くされています。被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
鬼怒川は群馬・栃木の県境に源を発し、利根川に合流する。流長170㌔。しばしば氾濫を繰り返したので治水工事が何度も繰り返されてきた。
度重なる氾濫被害の恐れから鬼怒と名付けられたのでしょう。
日本の軍艦名には河川名を付けられたものがあります。軍艦鬼怒もその一つ。
軍艦の種類もその用途によって多種に分かれるのですが、軍艦鬼怒は長良型に分けられ長良型5番艦です。(長良と同型、順番で5番目に建造されたという意味)
先にご説明しておきますが私も最近調べましたので軍オタでもなんでもないので詳しいことはわかりません。ただ学ばないといけないことだと思いますので、間違いがあればご教授願います。
*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪
それでは長良について書いていきます。
長良型はすべて河川名で名付けられました。長良型は順に「長良」「五十鈴」「名取」「由良」「鬼怒」「阿武隈」の6艦。
その中でも軍艦長良は型の名前にもなっている様に長良型一番艦ということで現在でも重要度と人気を集める存在。
軍艦鬼怒や軍艦長良と書いてきましたが、もっと詳しく分類したもので表記すると、
けいじゅんようかんながら
「軽巡洋艦長良」または省略して
けいじゅんながら
「軽巡長良」と呼ばれます。
軍艦に馴染みのない方々は軍の船いわゆる軍艦は全部戦艦(艦種戦類別戦艦)と思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか?私も恥ずかしながらそうでした。戦艦大和があまりにも有名すぎてその影響でしょう。
なので長良の事を一番誤用されやすいのが戦艦長良と呼ぶことだと思います。ここだけでも覚えていっていただけると牛深の方はわかってるなぁと思われると思いますので注意して覚えておいてください。よろしくお願いします。
大事なことなので2回言います、笑
「戦艦長良ではなく、軍艦長良もしくは軽巡長良」です!
経歴スペック(新造時)
大正11年4月21日竣工(佐世保工廠)
基準排水量:5170㌧
全長162.15㍍
速力:36.0㌩
兵装:14㌢砲7門、魚雷発射管8門、水偵1機


水雷戦隊の旗艦、主力部隊の直衛や前衛、艦隊後方の索敵(敵軍の位置・状況・兵力などをさぐる)、哨戒(敵の航空機,艦船が一定の空域,水域へ侵入するのを,哨戒機,哨戒艦艇,レーダ,見張り所などを用いて警戒する)などを任務にしていた。
長良川は岐阜県西部の大日岳に源を発し南流して木曽川、揖斐川と並んで伊勢湾に注ぐ。流長160㌔。
岐阜愛知と流れて伊勢湾に注いでいる長良川で、建造時には特別牛深と関係があるわけではありません。
何が関係しているのかというのは先日書いたこの記事の後半部分に載せた内容。
この内容にもう少し詳しいことを補足致します。
昭和19年8月7日に牛深大島沖で米潜水艦クローカー(USS Croaker, SS-246) の雷撃に遭い轟沈。
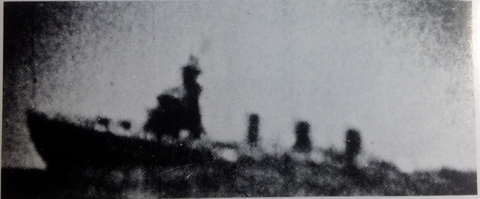
この写真は艦尾から沈みつつある長良を、クローカーが潜望鏡を通じて撮影したものです。
座標
北緯三十二度十二分
東経百二十九度五十一分
水深百二十七㍍
この轟沈した時は鹿児島から佐世保へ帰る途中だった。このことから長良は牛深沖を素通りしていただけで牛深に寄港したことなんて一度もないんだろうなと思っていました。
事実は違いました。長良は昭和3年12月に第一艦隊第三戦隊に編入され、その後は12年頃までしきりに中国のチンタオ方面で行動し、佐世保港への入港が頻繁でした。この時期牛深港に軽巡長良と軽巡夕張、その他駆逐艦などがしばしば碇泊していました。
「牛深ノ湾内ハ水深14尋(22,3㍍)アリテ、故ニ時々軍艦及ビ水雷艇ノ投錨セルヲ見ル」(我が町より)
湾内の水深は深く、湾の前面は島で視界を遮っていて敵に見つかりにくい上、天草灘の大海に直ぐ出ることができる。軍艦の碇泊には適地だった。昭和の軍測量牛深地図に詳しく一帯の水深が測定してあったのはこの理由からだったんだなと今わかった。
牛深港に長良が来ていたのだ。海彩館から港を眺め、長良を想う。
70年前の目の前の場所には長良がいたのだ。
フェリー乗り場で、見えないけどそこにいるような気がする長良に70年前の牛深の方と同じように僕は万歳ー!と叫んだ。
涙が頬を伝っていた。
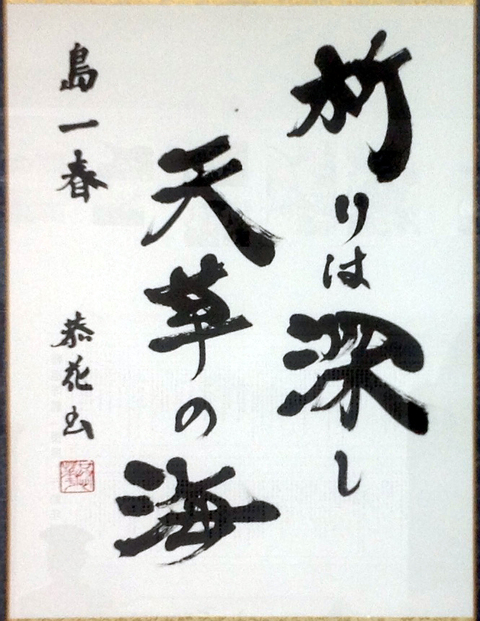
新聞記事内にある恭花さんの書です。
ということで第二回へ続くわけですが、この書にある島一春さんの本「天草灘にひびけ鎮魂の譜」を読みました。
涙無くしては読めない牛深の長良物語でした。次回はそこからおつるおばさんをご紹介したり、題名からもわかるように、若者に大人気の艦これの話題なんかボリュームたっぷり長文用意しています。次回読むときはハンカチも御用意ください(TдT)
な・の・で・す・が、牛深第十景なので私が絵を描かないといけなくて、笑。描きはじめてはいますが、まだまだ時間がかかりそうです。
ツイッターでは経過を報告しながらやっておりますのでご興味あられる方はTwitterのフォローをしていただけると描いている途中途中を公開してますので見てやってくださいな!
Twitterアカウントhirok_studio
右のTwitterからでもどうぞ!それではまた次回!→その2
はじめましての人ははじめまして!
「絵で見る~」の本についてはみなさんご注文いただき誠にありがとうございます。初版残り10冊ですお早めに!牛深の方は母へ言っていただけるとすぐお届けさせてもらいますm(__)m
今回は人気企画牛深八景の十作目。第十景でございます。題材は題名でお分かりの通り軍艦長良です。牛深に深く関係していて、まとめたいことが多くあるので2回に分けます。
昨日から鬼怒川の決壊でニュースは埋め尽くされています。被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
鬼怒川は群馬・栃木の県境に源を発し、利根川に合流する。流長170㌔。しばしば氾濫を繰り返したので治水工事が何度も繰り返されてきた。
度重なる氾濫被害の恐れから鬼怒と名付けられたのでしょう。
日本の軍艦名には河川名を付けられたものがあります。軍艦鬼怒もその一つ。
軍艦の種類もその用途によって多種に分かれるのですが、軍艦鬼怒は長良型に分けられ長良型5番艦です。(長良と同型、順番で5番目に建造されたという意味)
先にご説明しておきますが私も最近調べましたので軍オタでもなんでもないので詳しいことはわかりません。ただ学ばないといけないことだと思いますので、間違いがあればご教授願います。
*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪
それでは長良について書いていきます。
長良型はすべて河川名で名付けられました。長良型は順に「長良」「五十鈴」「名取」「由良」「鬼怒」「阿武隈」の6艦。
その中でも軍艦長良は型の名前にもなっている様に長良型一番艦ということで現在でも重要度と人気を集める存在。
軍艦鬼怒や軍艦長良と書いてきましたが、もっと詳しく分類したもので表記すると、
けいじゅんようかんながら
「軽巡洋艦長良」または省略して
けいじゅんながら
「軽巡長良」と呼ばれます。
軍艦に馴染みのない方々は軍の船いわゆる軍艦は全部戦艦(艦種戦類別戦艦)と思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか?私も恥ずかしながらそうでした。戦艦大和があまりにも有名すぎてその影響でしょう。
なので長良の事を一番誤用されやすいのが戦艦長良と呼ぶことだと思います。ここだけでも覚えていっていただけると牛深の方はわかってるなぁと思われると思いますので注意して覚えておいてください。よろしくお願いします。
大事なことなので2回言います、笑
「戦艦長良ではなく、軍艦長良もしくは軽巡長良」です!
経歴スペック(新造時)
大正11年4月21日竣工(佐世保工廠)
基準排水量:5170㌧
全長162.15㍍
速力:36.0㌩
兵装:14㌢砲7門、魚雷発射管8門、水偵1機


水雷戦隊の旗艦、主力部隊の直衛や前衛、艦隊後方の索敵(敵軍の位置・状況・兵力などをさぐる)、哨戒(敵の航空機,艦船が一定の空域,水域へ侵入するのを,哨戒機,哨戒艦艇,レーダ,見張り所などを用いて警戒する)などを任務にしていた。
長良川は岐阜県西部の大日岳に源を発し南流して木曽川、揖斐川と並んで伊勢湾に注ぐ。流長160㌔。
岐阜愛知と流れて伊勢湾に注いでいる長良川で、建造時には特別牛深と関係があるわけではありません。
何が関係しているのかというのは先日書いたこの記事の後半部分に載せた内容。
この内容にもう少し詳しいことを補足致します。
昭和19年8月7日に牛深大島沖で米潜水艦クローカー(USS Croaker, SS-246) の雷撃に遭い轟沈。
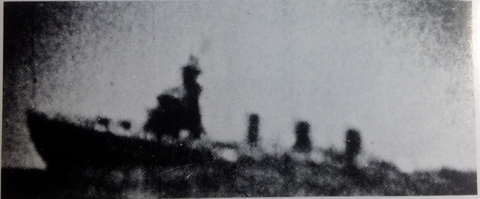
この写真は艦尾から沈みつつある長良を、クローカーが潜望鏡を通じて撮影したものです。
座標
北緯三十二度十二分
東経百二十九度五十一分
水深百二十七㍍
この轟沈した時は鹿児島から佐世保へ帰る途中だった。このことから長良は牛深沖を素通りしていただけで牛深に寄港したことなんて一度もないんだろうなと思っていました。
事実は違いました。長良は昭和3年12月に第一艦隊第三戦隊に編入され、その後は12年頃までしきりに中国のチンタオ方面で行動し、佐世保港への入港が頻繁でした。この時期牛深港に軽巡長良と軽巡夕張、その他駆逐艦などがしばしば碇泊していました。
「牛深ノ湾内ハ水深14尋(22,3㍍)アリテ、故ニ時々軍艦及ビ水雷艇ノ投錨セルヲ見ル」(我が町より)
湾内の水深は深く、湾の前面は島で視界を遮っていて敵に見つかりにくい上、天草灘の大海に直ぐ出ることができる。軍艦の碇泊には適地だった。昭和の軍測量牛深地図に詳しく一帯の水深が測定してあったのはこの理由からだったんだなと今わかった。
牛深港に長良が来ていたのだ。海彩館から港を眺め、長良を想う。
70年前の目の前の場所には長良がいたのだ。
フェリー乗り場で、見えないけどそこにいるような気がする長良に70年前の牛深の方と同じように僕は万歳ー!と叫んだ。
涙が頬を伝っていた。
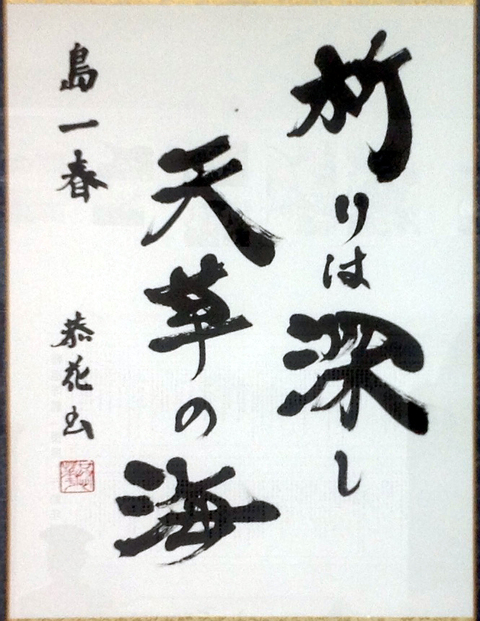
新聞記事内にある恭花さんの書です。
ということで第二回へ続くわけですが、この書にある島一春さんの本「天草灘にひびけ鎮魂の譜」を読みました。
涙無くしては読めない牛深の長良物語でした。次回はそこからおつるおばさんをご紹介したり、題名からもわかるように、若者に大人気の艦これの話題なんかボリュームたっぷり長文用意しています。次回読むときはハンカチも御用意ください(TдT)
な・の・で・す・が、牛深第十景なので私が絵を描かないといけなくて、笑。描きはじめてはいますが、まだまだ時間がかかりそうです。
ツイッターでは経過を報告しながらやっておりますのでご興味あられる方はTwitterのフォローをしていただけると描いている途中途中を公開してますので見てやってくださいな!
Twitterアカウントhirok_studio
右のTwitterからでもどうぞ!それではまた次回!→その2










